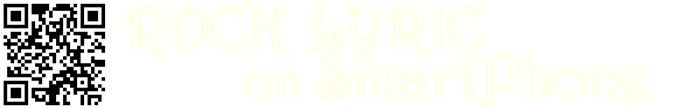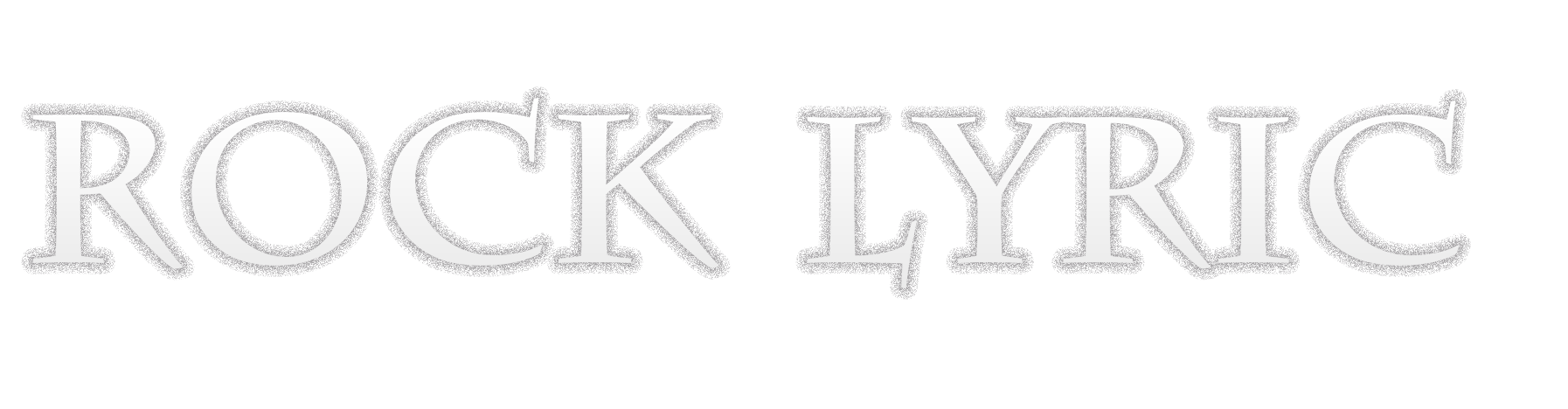2013-12-20
【THE TON-UP MOTORS】もう一度ここから新しく始める気概で作ったメジャー1stアルバム

ソウル・ファンクマナーたっぷりのサウンドと情熱的でソウルフルな歌で13年。北海道出身の4人組THE TON-UP MOTORSが、自らのグループ名を冠したアルバムを発表した。熱きソウルマン上杉周大(Vo)が作品に込めた思いを語る。
──まずは結成の経緯と現在までのいきさつを教えてください。
「幼馴染だった長谷川(Ba/リーダー)に、“歌ってくれ”と誘われたのがきっかけで。18歳の時でした。そこからメンバーチェンジを経て、今のメンバーに至ってます。ちなみに僕と長谷川と井上(Gu)が北海道出身、堀内(Dr)は千葉出身なんですけど、総称して北海道出身の4人組と(笑)。」
──今はソウルミュージックやR&B、ファンク色の強い音楽性ですが、もとからこのような音楽を?
「いえいえ。もともとパンクやガレージが好きだったこともあり、結成当初はそういった音楽性でした。」
──そこから今の音楽性への移行は?
「上に兄貴がいて、その影響でローリング・ストーンズやブルースをルーツに持つバンドを好んで聴いてたんで、潜在的には今のような素養はあったと思います。大学に入ってさらにパンクのもとを掘り下げていくようになって。そんな中、気付いたんですよね。爆音で鳴らしたりカマしたりするより、魂を込めて熱く歌ったほうが、よっぽどロックなんじゃないかって。そこからはブラックミュージックどっぷりになりました。」
──ノリと勢いの世界からグルーブや跳ねを大事にした今のような音楽性への移行は大変だったのでは?
「最初はそれこそマネから入りましたよ。とはいえ、今でもそこを求道的に突き詰めてるというよりは、それらを用いて、よりポップに聴いている人に伝えることを目指してる感じかな。それをより感じさせたくて、間にソウルマナーのフェイクを盛り込んだり。なので、ステージでもエンターテインメント性はかなり重視してます。常に目の前のお客さんを引き込み、巻き込み、どれぐらい楽しませられるか、対バンのバンドにいかに勝つか、そんなことばかり考えてきた13年でした(笑)。」
──結成13年ですもんね。
「その“13年”と聞くと苦労人みたいだけど、当人としては好きな音楽をずっとやってこれたんで、結構あっと言う間でしたよ。もちろん辞めたり、足を洗ったりも周りでこれまでたくさん見てきたけど、彼らが諦めたものや描いていた夢の分まで、“じゃあ、俺が代わりに叶えてやる!!”と勝手に背負ってきたところもあって(笑)。」
──では、メジャーデビューを果たした今は逆に達成感があるのでは?
「いやいや。そんなに甘い世界じゃないですから。ようやく新しいスタートラインに立てたとしか思ってないです。これまで以上に結果にシビアになるだろうし。」
──話を楽曲に。上杉さんの作る歌世界にはすごくカッコ良さも見苦しさも含めた表裏が曝け出されていて、非常に“男の唄”的なものを感じます。
「感情を歌うことを大事にしてますからね。良いものも悪いものも吐き出して、すごく弱い自分や情けない自分も歌うように心掛けてます。ソウルミュージック自体が喜怒哀楽を歌っている音楽ですからね。そんな中、日常で強く感じていることを素直に歌詞にしたためてる感じです。よく“ストレートすぎる”“トゥーマッチだ”と言われますけど、逆にそれがこのTHE TON-UP MOTORSの魅力かなと。賢くないだろうけど、ありもしないことは歌いたくない。特に今回のアルバムは、その辺りも詰め込めましたね。」
──今作はTHE TON-UP MOTORSの真骨頂と、今までになかった部分の同居を感じました。
「まさしくそれで。アルバムタイトルに自分たちの名を付けているように、もう一度ここから新しく始める気概で作りました。4人で“自分たちってどんなバンドなのか?”を見つめ直して、考え、今までのライヴで培ってきた自分たち、そして何か新しいこれからの自分たちを裏切らない範囲で入れ込めたのが今作なんです。なので、アルバムのうち数曲は初挑戦の試みだったりしますよ。」
──それは「街の灯り」のことですか?
「それもそうですね。これはドラムの堀内が初めて作曲をして、作詞も僕との共作なんです。歌い方もこれまでと違い、あえて抑え目で秘めた情熱を表してみました。新鮮でしたね。あと、「愛してる」。これも歌い方の挑戦でした。これらで新しい自分に出会えたし。そうそう、最後の「それが愛さ」はまさに全員参加の曲で、歌詞も4人で作ったんです。この曲はメンバー各人が抱いているさまざまな愛を持ち寄って歌にしたもので。なので、全員でヴォーカルをとってるんです。ほんとこれらは新機軸でしたね。作詞作曲の面では、もちろんこれからも僕が主軸だろうけど、4人で作り上げることも大事にしたいなと思いました。それによる自分にはなかったバリエーションや幅を得られることも学んだし。」
──対して前半の「準備OK」や「ファイティング・ステップ」などは、これまでのTHE TON-UP MOTORSを強く感じました。
「この辺りはこれまでの自分たちもですけど、自らのルーツもあえて色濃く入れ込んでみました。まさにいろいろな角度から見たTHE TON-UP MOTORSが詰まっている感じ。自分たちが受けたブラックミュージックの洗礼を、できるだけ分かりやすく、伝わりやすく、ポップに、それらの素晴らしいエッセンスを8ビートやロックンロール、疾走感のあるサウンドに乗せて届けることも意識しました。なので、逆に僕らを入口にソウルミュージックなどを知ってもらえると嬉しいですね。」
──では、ソウルミュージックへの啓蒙者的存在でありたいと?
「そこまで大げさじゃないですけど(笑)、あえて間口を広く持っているところもあります。そんなにコアな音楽ファンじゃない人にも向けているところもあるし。そういった方々が聴いて、“ちょっと変わってる”“面白い”“クセになる”、そんな感想を持ってもらえると本望ですね。“おっ、俺たちのソウルや叫びが伝わったな”って。僕の思うソウルミュージックって案外そんなもんだったりするんです。」
取材:池田“スカオ”和宏
(OKMusic)
記事リンクURL ⇒
※この記事をHPやブログで紹介する場合、このURLを設置してください。
新着ニュース
-
 umbrella、柊(G)生誕祭ライヴをheidi.を迎えてツーマンで開催決定2024-05-01
umbrella、柊(G)生誕祭ライヴをheidi.を迎えてツーマンで開催決定2024-05-01 -
 Zeke Deuxの最新ビジュアルは、古の軍服姿。そこへ隠された意図とは…。2024-05-01
Zeke Deuxの最新ビジュアルは、古の軍服姿。そこへ隠された意図とは…。2024-05-01 -
 MUCCの逹瑯 LIVE HOUSE TOUR [The COLORS] LIQUIDROOMライヴレポ2024-04-30
MUCCの逹瑯 LIVE HOUSE TOUR [The COLORS] LIQUIDROOMライヴレポ2024-04-30 -
 SHAZNAの30周年公演は、30年間の歩みを彩る名曲ばかりが並んだ神セトリ公演。2024-04-27
SHAZNAの30周年公演は、30年間の歩みを彩る名曲ばかりが並んだ神セトリ公演。2024-04-27 -
 MUCC 結成日に27周年突入記念番組「徹底解剖!『愛の唄』&『Love Together』」Yo...2024-04-27
MUCC 結成日に27周年突入記念番組「徹底解剖!『愛の唄』&『Love Together』」Yo...2024-04-27 -
 シドのAKi、待望のニューアルバムのタイトル&リリース日が決定!新アーティスト...2024-04-27
シドのAKi、待望のニューアルバムのタイトル&リリース日が決定!新アーティスト...2024-04-27 -
 D'ERLANGER、ニューアルバム「Rosy Moments 4D」のサブスクリプション配信が4月2...2024-04-24
D'ERLANGER、ニューアルバム「Rosy Moments 4D」のサブスクリプション配信が4月2...2024-04-24 -
 シド・ヴォーカル マオによるソロプロジェクトが新たにスタート!2024-04-22
シド・ヴォーカル マオによるソロプロジェクトが新たにスタート!2024-04-22 -
 「いじくらNIGHT Vol.3 ~コドモにもどって、はっちゃけナイト!~」ゲスト解禁!2024-04-22
「いじくらNIGHT Vol.3 ~コドモにもどって、はっちゃけナイト!~」ゲスト解禁!2024-04-22 -
 「燃えこれ学園始業式&青山明日香生誕祭」公演2024-04-22
「燃えこれ学園始業式&青山明日香生誕祭」公演2024-04-22 -
 チケットはSold Out。今、大勢の人たちが、Siriusというガールズメタルシーンに...2024-04-17
チケットはSold Out。今、大勢の人たちが、Siriusというガールズメタルシーンに...2024-04-17 -
 MUCC 徳間ジャパンコミュニケーションズ移籍第1弾シングル「愛の唄」発売記念イ...2024-04-17
MUCC 徳間ジャパンコミュニケーションズ移籍第1弾シングル「愛の唄」発売記念イ...2024-04-17 -
 DEZERTがPARTY ZOO、M.A.Dを再始動!2024-04-17
DEZERTがPARTY ZOO、M.A.Dを再始動!2024-04-17 -
 ミスイ単独公演「弱歌斉唱」は、歌モノに特化したスペシャルな内容。当日限定の...2024-04-15
ミスイ単独公演「弱歌斉唱」は、歌モノに特化したスペシャルな内容。当日限定の...2024-04-15 -
 若手ヴィジュアル系対バンシリーズ「KHIMAIRA」の第2弾&第3弾にRoyz、DaizyStri...2024-04-15
若手ヴィジュアル系対バンシリーズ「KHIMAIRA」の第2弾&第3弾にRoyz、DaizyStri...2024-04-15 -
 シド、アニメ『黒執事 -寄宿学校編-』エンディングテーマ「贖罪」Music Video公開!2024-04-15
シド、アニメ『黒執事 -寄宿学校編-』エンディングテーマ「贖罪」Music Video公開!2024-04-15 -
 シド・ゆうや、ソロワークのアーティスト名を「S.Yuya」に改め、1stアルバムリリ...2024-04-15
シド・ゆうや、ソロワークのアーティスト名を「S.Yuya」に改め、1stアルバムリリ...2024-04-15 -
 MUCC TOUR 2024「Love Together」全10組のサポートバンド解禁!チケットFC先行受...2024-04-12
MUCC TOUR 2024「Love Together」全10組のサポートバンド解禁!チケットFC先行受...2024-04-12
アーティスト・楽曲・50音検索
人気歌詞ランキング