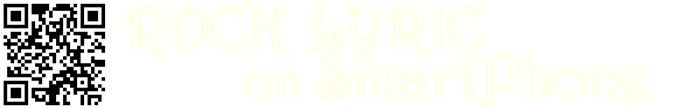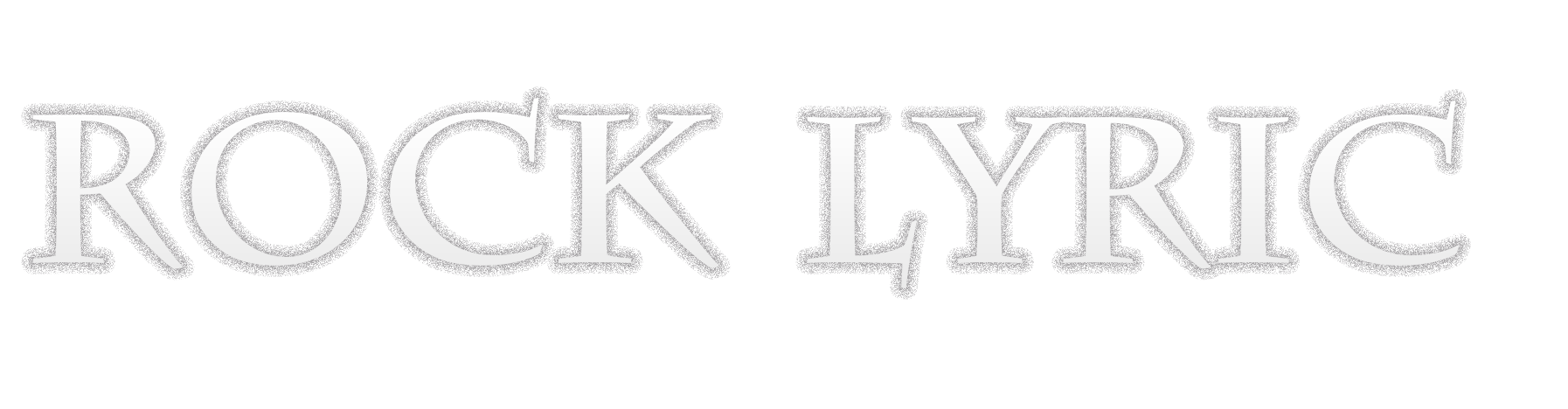2011-07-20
DIR EN GREY、暗闇に差し込む一筋の光明

最高傑作との呼び声も高かった前作『UROBOROS』から2年9カ月、通算8作目となるアルバム『DUM SPIRO SPERO』が完成。日本を含む世界21カ国でほぼ同時にリリースとなる本作は、渾沌とした暗闇とその中に差しこむ一条の希望の光を想起させる。
──アルバムタイトルはラテン語の格言で“息ある限り希望を捨てず”という意味だそうですね。
薫 これは外に向けたメッセージであると同時に自分たちに向けたものでもあって。バンドを始めて15年、アルバムは今回が8枚目となるわけですが、どういったものにするかといった中で、葛藤や悩みがありました。そこで、新しい何かを作り出すことによって先が見えてくるんじゃないか、という希望をこのアルバムに託した部分があるんです。俺たちにその気持ちがあったからこそ、聴いてくれる人たちに“自由に捉えてもらっていいよ”と言えると思うし、アルバムのタイトルにすることができたんじゃないかと。
Die 最後の最後にこの言葉が出てきた時に、まるで導かれるかのようにスッと決まったんです。きっと、俺たち自身が求めていた言葉だったんでしょうね。アルバム完成間近の頃に震災があって、このまま制作作業を続けるべきか否かという判断を迫られる局面で、俺たちは“ここまで作り続けたんだから必ず完成させる!”という決意を持って作業を続行したんです。その経験があったこともタイトルに重みを持たせているように思います。
──楽曲のプリプロダクションの方法がとてもユニークだったそうですね。詳しく教えてください。
薫 ひとつの大きな部屋に全員が集まり、それぞれがMacにその場でアイデアを演奏して取り込み、そのファイルを中心となるメインのマシンに送る。それをマニュピュレーターが土台となる曲に貼り付けていくという方法でした。お互いのアイデアを確認しながらアレンジがどんどん変化していくんですけど、同じ部屋にいるのに全員ヘッドフォンをして違う方向を向いて、会話も一切ないという(笑)。
──そういった曲の作り方とも関係あるのかもしれませんが、アレンジの複雑さと音の重ね方は、ライヴでの再現を想定していないように感じました。
Die そういう縛りは一切ないんで。まったくライヴのことを考えていないということはないけど、スタジオでの作業中はそういう意識を超越してますね。
薫 “ライヴでどうしようかな?”と頭の片隅で考えてるけど、思い付いたものはしょうがないや、って(笑)。
──今回は京さんのヴォーカルが特にバラエティーに富んでいますね。グロウル、スクリーム、ハイトーン、クリーン、しかもそれらが重なっていたり。これ、ライヴでどう再現するんだろうなって思いました(笑)。
薫 歌ってくれって言われるんですよ。実際はそんな簡単にはいかないですけど(笑)。
Die “誰かが歌ってくれるなら、このアレンジにしようかな?”とか言われるとイヤとは言えない(笑)。その時は“誰かが歌うんだろうな”ぐらいの気持ちなんだけど、実際に誰が歌うか決める時になると“うーん”って(笑)。変なリズムで入ってきたりすると手元がおろそかになりますからね。
──アルバムの制作期間中にはライヴもかなりの本数やっていますが、ライヴで曲を試すようなことはないのですか?
薫 ないですね。曲に関する情報をあまり教えたくないんですよ。曲の存在を知られたくない(笑)。初めて聴いた時に全てが初めての状態で聴かせたいんです。こうして取材をしてもらっていますけど、本当は発売前に喋っていろんな情報を知ってもらいたくもないんですよ(笑)。
──それは申し訳ありません(笑)。「DIFFERENT SENSE」と「VANITAS」の2曲にギターソロが入っていますよね。ここ最近のDIR EN GREYにとっては珍しいと思うのですが。
薫 「DIFFERENT SENSE」は俺、「VANITAS」はDieが弾いています。ここ何年かは、曲が始まったら一番手前にヴォーカルが絶えず存在するという曲がほとんどだったので、たまには違う人間の空気感が前に出ることがあってもいいかなと思って。そうすることでこのアルバムが持つリアルな感じに持っていけるんじゃないかなと。
──あと、これだけ曲の展開が複雑だと、特にドラムの録りは大変だったのでは?
Shinya ドラムって他の楽器よりも先に録るから、曲ができてから録りまでの時間がそんなにないじゃないですか。その間に、暗記力を発揮して憶えるんです(笑)。
──アルバム全編に渡り、ヘヴィなサウンドでありながら、これまで以上にクリーンで、それぞれの楽器の音が鮮明に聴こえましたが、これはチュー・マッドセンのミックスによるところも大きいのでしょうか?
薫 録りの段階からある程度音の位置を決め込んで作っていったのはあるけど、彼のミックスは一発目が帰ってきていきなり満足でした。予想以上にはまっていて。
Shinya 「LOTUS」の時はミキシングエンジニアと何度もやりとりをしなければならなかったけど、今回は一発目からいきなり好みの音でしたね。だから、やりとり自体がとても早かった。
Die 今までになかったぐらいの衝撃を受けましたよ。自分たちが目指していた音に極めて近くて。ひとつひとつの音がクリーンで早い。ものすごいスピードで音が飛んでくる。
──アルバムを完成させた今、それぞれの目にはこのアルバムはどのように映っていますか?
Die 自分が完全に外部の人間として見たら、聴いたことがない音なんじゃないかな。こんな世界見たことない、って。
Shinya …不思議なアルバム(笑)。
薫 まだ客観的になれていなくて。正直、どういうアルバムか分かっていなですね。個人的には勝負に出たアルバムという部分が大きいんです。自分が信じた道をわりとストレートに出したつもりなんで、反応が怖いというのはあるかな。それが本当にバンドとして正解なのか、まだ自分の中で分かっていない。アルバムとしてのバランスを無視してやりたい放題やった感が強かったし。自分たちにしかできないバランス感覚で成り立っていると思うので、それをみんながどう捉えるかが、気になるといえば気になります。
取材:金澤隆志
記事提供元:
記事リンクURL ⇒
※この記事をHPやブログで紹介する場合、このURLを設置してください。
DIR EN GREY 新着ニュース・インタビュー
新着ニュース
-
 Petit Brabancon、新曲「haunted house」をツアー来場者限定先行解禁2026-03-03
Petit Brabancon、新曲「haunted house」をツアー来場者限定先行解禁2026-03-03 -
 ミスイ、5月20日に3rdミニアルバムを発売。6月と7月には天音とLANA-ラナ-のバー...2026-03-02
ミスイ、5月20日に3rdミニアルバムを発売。6月と7月には天音とLANA-ラナ-のバー...2026-03-02 -
 悲報発表の当日、Billboard Liveツアー開幕のINORAN 真矢のレガシーを受け継ぎ「...2026-02-27
悲報発表の当日、Billboard Liveツアー開幕のINORAN 真矢のレガシーを受け継ぎ「...2026-02-27 -
 wyolicaのボーカルAzumi 自身ソロの代表曲「Carnival」が全国のカラオケパセラに...2026-02-26
wyolicaのボーカルAzumi 自身ソロの代表曲「Carnival」が全国のカラオケパセラに...2026-02-26 -
 CHAQLA. 夏にニューアルバム発売決定&8月2日キネマ倶楽部ワンマンライヴ「超音...2026-02-25
CHAQLA. 夏にニューアルバム発売決定&8月2日キネマ倶楽部ワンマンライヴ「超音...2026-02-25 -
 umbrella、、4月30日にベーシスト・春(B)の生誕祭ワンマンライブを開催決定2026-02-25
umbrella、、4月30日にベーシスト・春(B)の生誕祭ワンマンライブを開催決定2026-02-25 -
 DRUGS 2nd ONEMAN 【 THE NORMAL 】 2026年2月17日(火) Spotify O-WEST2026-02-25
DRUGS 2nd ONEMAN 【 THE NORMAL 】 2026年2月17日(火) Spotify O-WEST2026-02-25 -
 ULTRA-PRISM「Say 全 魂-soul-」 第一部2026-02-25
ULTRA-PRISM「Say 全 魂-soul-」 第一部2026-02-25 -
 AKi(シド)、誕生日&10周年を記念したリクエストワンマンライブレポ2026-02-24
AKi(シド)、誕生日&10周年を記念したリクエストワンマンライブレポ2026-02-24 -
 Z CLEAR、5月6日に発売する1stアルバム『至大至剛』を、3月より始まる全国ワンマ...2026-02-24
Z CLEAR、5月6日に発売する1stアルバム『至大至剛』を、3月より始まる全国ワンマ...2026-02-24 -
 3/10(火)発売!!『世界ヴィジュアル系ガイドブック』 世界30の国と地域からアーテ...2026-02-24
3/10(火)発売!!『世界ヴィジュアル系ガイドブック』 世界30の国と地域からアーテ...2026-02-24 -
 SAMMY(BILLY AND THE SLUTS)の還暦を祝うライブに、同じ90年代のヴィジュアルシ...2026-02-23
SAMMY(BILLY AND THE SLUTS)の還暦を祝うライブに、同じ90年代のヴィジュアルシ...2026-02-23 -
 fuzzy knot、Shinji(G)のバースデーライブレポ2026-02-19
fuzzy knot、Shinji(G)のバースデーライブレポ2026-02-19 -
 新しい世界へと踏み出すRuiza(D)の強い意志と決意を示した、フルアルバム『A New...2026-02-18
新しい世界へと踏み出すRuiza(D)の強い意志と決意を示した、フルアルバム『A New...2026-02-18 -
 2月19日(木)19時『いじくりROCKS!』#72 追加情報! DEZERTの新曲をプロデュー...2026-02-17
2月19日(木)19時『いじくりROCKS!』#72 追加情報! DEZERTの新曲をプロデュー...2026-02-17 -
 DEZERTが、Ken(L'Arc-en-Ciel)プロデュースによる新曲『「音楽」』をリリース!2026-02-17
DEZERTが、Ken(L'Arc-en-Ciel)プロデュースによる新曲『「音楽」』をリリース!2026-02-17 -
 新生HOT DOG CAT、初の新曲披露公演で、1周年ワンマン公演を発表!!2026-02-12
新生HOT DOG CAT、初の新曲披露公演で、1周年ワンマン公演を発表!!2026-02-12 -
 2月19日(木)19時『いじくりROCKS!』#72 ゲストには3月に幕張メッセでのワンマ...2026-02-12
2月19日(木)19時『いじくりROCKS!』#72 ゲストには3月に幕張メッセでのワンマ...2026-02-12
アーティスト・楽曲・50音検索
人気歌詞ランキング
新着コメント
TUBE / 『あー夏休み』
владимир воронин семья
シェリル・ノーム starring May'n / 『ダイアモンド クレバス/射手座☆午後九時 Don't be late』
Взглянем на XCARDS — сервис, о
котором сейчас говорят.
Совсем недавно наткнулся о цифровой сервис
XCARDS, он дает возможность
создавать онлайн дебетовые карты
чтобы контролировать расходы.
Особенности, на которые я обратил внимание:
Создание карты занимает очень короткое время.
Сервис позволяет выпустить множество
карт для разных целей.
Поддержка работает в любое время суток включая персонального менеджера.
Доступно управление без задержек —
лимиты, уведомления, отчёты, статистика.
На что стоит обратить внимание:
Локация компании: европейская юрисдикция — перед использованием стоит уточнить,
что сервис можно использовать без нарушений.
Комиссии: в некоторых случаях встречаются оплаты за операции, поэтому советую просмотреть договор.
Реальные кейсы: по отзывам поддержка работает быстро.
Защита данных: все операции подтверждаются уведомлениями, но всегда
лучше не хранить большие суммы на карте.
Общее впечатление:
Судя по функционалу, XCARDS может стать
удобным инструментом в сфере финансов.
Платформа сочетает скорость, удобство и гибкость.
Как вы думаете?
Пробовали ли подобные сервисы?
Напишите в комментариях Виртуальные карты для бизнеса
シェリル・ノーム starring May'n / 『ダイアモンド クレバス/射手座☆午後九時 Don't be late』
Что такое XCARDS — сервис, о котором сейчас говорят.
Буквально на днях заметил о интересный бренд XCARDS, он помогает создавать онлайн карты чтобы управлять бюджетами.
Ключевые преимущества:
Выпуск занимает всего считанные минуты.
Платформа даёт возможность оформить множество карт для разных целей.
Есть поддержка в любое время суток включая персонального менеджера.
Есть контроль без задержек — транзакции, уведомления, аналитика — всё под рукой.
Возможные нюансы:
Регистрация: европейская юрисдикция — желательно убедиться, что
сервис можно использовать без
нарушений.
Финансовые условия: возможно,
есть скрытые комиссии, поэтому лучше внимательно прочитать договор.
Отзывы пользователей: по отзывам поддержка работает быстро.
Надёжность системы: внедрены базовые меры безопасности, но всё равно советую не хранить большие суммы
на карте.
Вывод:
В целом платформа кажется
отличным помощником для маркетологов.
Платформа сочетает скорость, удобство
и гибкость.
Как вы думаете?
Пользовались ли вы XCARDS?
Поделитесь опытом — будет интересно сравнить.
Виртуальные карты для бизнеса
シェリル・ノーム starring May'n / 『ダイアモンド クレバス/射手座☆午後九時 Don't be late』
Взглянем на XCARDS — платформу, которая меня заинтересовала.
Буквально на днях услышал на новый проект XCARDS, он помогает создавать цифровые банковские карты для онлайн-платежей.
Основные фишки:
Карту можно выпустить за ~5 минут.
Платформа даёт возможность создать
любое число карт — без ограничений.
Поддержка работает круглосуточно включая живое
общение с оператором.
Доступно управление в реальном времени — лимиты, уведомления, отчёты, статистика.
Возможные нюансы:
Локация компании: европейская юрисдикция
— желательно убедиться, что это соответствует местным требованиям.
Стоимость: карты заявлены как “бесплатные”, но дополнительные сборы, поэтому рекомендую внимательно прочитать договор.
Реальные кейсы: по публикациям на форумах поддержка работает
быстро.
Надёжность системы: сайт использует шифрование, но всё
равно советую не хранить большие суммы
на карте.
Общее впечатление:
В целом платформа кажется
удобным инструментом в онлайн-операций.
Он объединяет удобный интерфейс,
разнообразие BIN-ов и простое управление.
Как вы думаете?
Пробовали ли подобные сервисы?
Расскажите, как у вас работает Виртуальные карты для онлайн-платежей
シェリル・ノーム starring May'n / 『ダイアモンド クレバス/射手座☆午後九時 Don't be late』
Вау, прекрасно веб-сайт. Спасибо...
Посетите также мою страничку
Квартиры на сутки