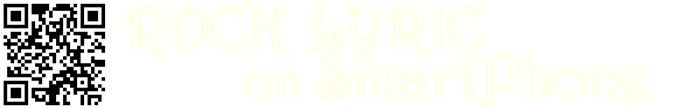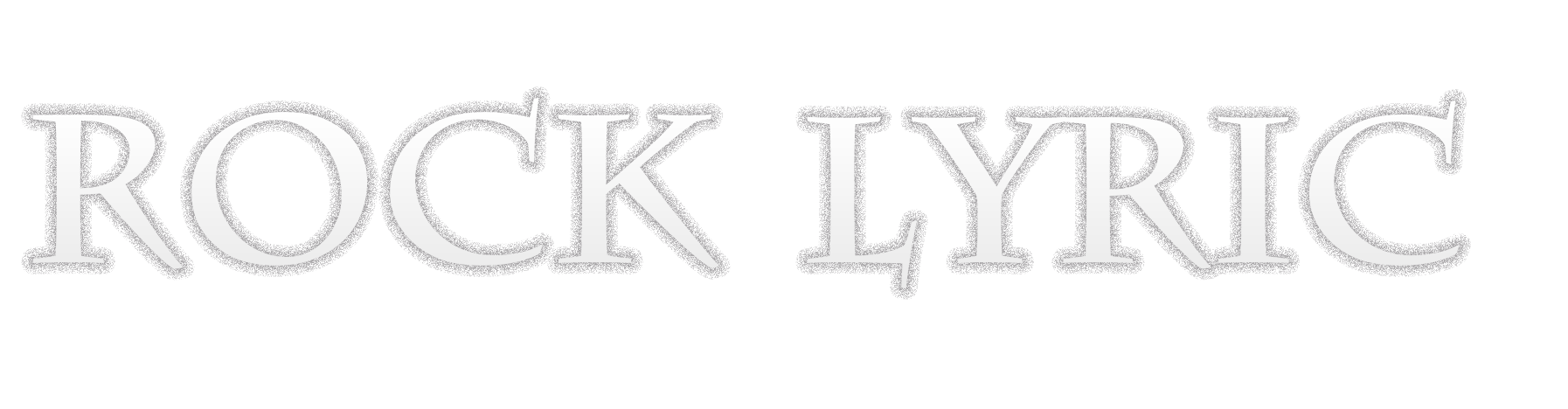2014-01-20
【NICO Touches the Walls】“今現在進行形”のベストアルバム完成!

NICO Touches the Wallsの2014年は、自身初のベスト盤で幕開けだ。2度目の武道館公演決定など今年も意欲的な活動にまい進する彼らは、未来へ向かって駆け抜け続ける姿勢をあくまでも貫く。その思いが凝縮した今作の誕生秘話をお届けしよう。
【武道館に絶対リベンジしてやろう それがベスト盤のきっかけでした】
──初のベスト盤はCDだけでも十二分に堪能できますけど、初回盤のDVDはインディーズ時代のミニアルバム『Walls Is Beginning』を全曲スタジオライヴで再現するっていう形式がすごく面白いですね。
光村「はい。まず、ベスト盤の話は2014年に武道館をやろうっていうのがきっかけになったんです。俺らの中では、4年前、2010年に武道館を初めてやった時にめちゃくちゃ緊張しちゃってて、心の底から本当に武道館を楽しめたかなって言ったらそうではなかったなっていう。だから、絶対リベンジしてやろうってずっと思ってたんです。」
坂倉「うん。とにかく悔しいんですよね。」
光村:「僕もそうだし、古村くんに関しては“記憶がない”っていう、そういうことも言ってますから(笑)。」
古村「(笑)。はい…あがりすぎて記憶がないんです。」
光村「だからね、古村くんに武道館を記憶してもらうためにも(笑)、武道館に向けて面白いことを2014年はいろいろやろうと思ってて。あと、2013年に5thアルバム『Shout to the Walls!』を出せたこともすごく大きかったんですけど、バンドとして自信もついてきたから、今ならリベンジかけてみてもいいんじゃないかなと思って8月に武道館を決めたっていうのがそもそもあって。じゃあ、武道館にもう一度立つために、“これがNICOなんです”っていう自分たちの名刺をもう1回作るべきなんじゃないかっていうのが、ベスト盤を出そうって話になったきっかけだったんですよね。だから、いっぱい曲をリリースしました、アルバム5枚出しましたっていう、曲が溜まったから出すベストみたいなものを作る気はさらさらなかったんです。僕たちが活動の基盤としているライヴでお客さんと一緒に作り上げてきた文化みたいなものがギュッと凝縮したものを出すべきなんじゃないかっていうのが、そもそものきっかけで。」
対馬「ライヴで盛り上がる曲をチョイスするっていうのを踏まえてるので、俺らのライヴはこういう曲で盛り上がってきたっていう意味での歴史はもちろん詰まってるんですけどね。でも、1曲目から新曲(「ローハイド」)で入ってることからして、今の俺たちはこういう感じで走ってます、こういうカッコ良いベストを作りました、この先が気になるだろ?っていうベストなんです(笑)。ざっくり言うと、ですけど。」
──そうですね。アッパーな曲が多いなっていうのがまず第一印象にはありました。あと、「Mr.ECHO」みたいな合唱が沸き起こるライヴの絵が想像できる曲もあったり。
光村「そうですね。選曲基準は、とにかくライヴでポイントになってるもの。シングルになっていない曲も入ってますけど、ライヴではみんなで歌ったり…「バイシクル」なんかはまさにそうだし、「N極とN極」はライヴではアンコールと最後にやったりする大事な曲だし。ライヴでポイントになってるそういう曲は、お客さんのリアクションがあったからこそ今そうなってるんですよね。ベスト盤はそういう選曲にして、しかも2枚組じゃなく絶対CD1枚にしたい。そう考えた時に、インディーズの曲も入れていくと収集がつかなくなってきちゃって(笑)。だから、ベスト盤のCDはメジャーデビューしてからのものを入れて、インディーズの曲はDVDにしようっていうのがそもそもの始まりでしたね。」
──新曲で始まり新曲で終わるっていう構成もそうですし、DVDはDVDで、それこそこのバンドの始まり、『Walls Is Beginning』の曲をスタジオライヴで再現するっていうことも、単に懐かしむ内容じゃないっていう姿勢を感じます。
坂倉「CDのほうの選曲してた時も、どの曲もライヴでやってて核になってた曲たちなんで、“こんな曲あったなー”っていう懐かしさは全然なかったですね。だから、僕らのライヴにずっと来てなかった人とか、もっといろんな人たちに今の自分たちを知ってほしいんですよ。これを聴いてもらえれば、僕らのライヴは間違いなく伝わるというか。もう本当に、今現在進行形っていう感じがしてるんですよ、このベストは。」
光村「そうだね。逆に、DVDでやったスタジオセッションの曲は、ものすごく新しく生まれ変わっちゃったなっていう(笑)。“懐かしいなー!”って感じは本当になかったし、むしろインディーズの時よりも今のほうが、この時の曲をやるなら説得力あるんじゃないかって思っちゃったくらい。」
──それは分かる気がします。「病気」みたいな曲調は、キャリアを重ねれば重ねるほど味が出るんじゃないかなって。
坂倉「そうですね。4人で合わせた時に、“当時の曲、シブッ!”って思った。」
光村「(笑)。8年前、俺らが二十歳の時ですからね。」
坂倉「比較的、“まんま”やってるんだけどね。」
光村「うん。比較的忠実にやろうとはしてるんだけど、ただでさえインディーズの時は結構いっぱいダビングしたり、 “レコーディング芸”のようなものをかなり使ってましたから。でも、今回のスタジオセッションは4人きりで、ギターも2本で、みたいなところではリアレンジしたりとか。「そのTAXY,160km/h」とかも尺が伸びてたり、細かいところは今のバージョンでやってるんですけど、本当に8年前とは思えないほど楽しくやれちゃって、ね!」
古村・坂倉・対馬「うん!」
光村「まぁ、当時としては…というか、気持ちは今と変わってないですけど、とにかく世の中にカウンターとしての王道を打ってやろうっていう気持ちでやってたんですよね。それが、いかに特殊なことをやっていたかっていうのは今になって、久しぶりに演奏してやっと分かりました(笑)。」
【これからの始まりを最高のやり方で表現する】
──王道っていうと、普通はポップでみんなで歌えるキャッチーさとかそういうことになる気がしますけど、NICOの王道はそうじゃないっていうところに特殊性を感じます。
坂倉「当時は、今言ってたような“みんなで歌えて”みたいな文化は、自分たちの中にはなかったかもしれないですね。特に僕はライヴに行ってみんなで手をあげて、みたいなことをしてこなかった人間で、家でひとりでネチネチ音楽を聴いてるような少年だったので(笑)。好きな外国のバンドがテレビに出てたりすると喜んでたりはしてたんですけど、でも、そこに自分が参加して、周りを気にせず手をあげてとかっていうのが、当時はあまり想像できなかったというか。」
光村「うん。その当時、僕らも出てた下北とか渋谷のライヴハウスは、いわゆる流行りの“4つ打ち”系の踊れる曲とかをやっていたバンドが多々いて、それに合わせて決まった振りがあって、みたいな。そういう状況のほうが、俺らからしたら特殊な気がしてたんですよ。俺、もともとサザンオールスターズが好きで、サザンのライヴを観たりとかCD聴いたりすると、ものすごい音楽知識が凝縮されてるわけじゃないですか。王道ってそうあるべきだよなっていうのが自分の価値観だったし、それがエンタテインメントだと今でも思ってるから。で、そういうものを、もうとにかく真正面からずーっと投げ続けてたのがインディーズ時代だったんですよね。」
──周りに迎合しない感は、確かにあったかもしれないですね。“この年齢でこのシブさ?”みたいな感覚は、自分たちの流儀を貫く姿勢の表れだったような気もしますし。
光村「俺らが楽しくないですからね、そうじゃないと。ライヴでよくある決まりごととかよりも、心のもっと奥底の扉を開放する感じだったりがずっとテーマで、そこからこのバンドは始まったし。最初はそれが上手く伝わらなかった部分もあったけど、でも、今なら伝えられるなと思ったんで。」
古村「まず『Walls Is Beginning』があって、それを今の自分たちで表現しているDVDがあって、そこからメジャーでリリースしてきた作品がこのベストでひとつのかたちになってるんですけど。今までいろんなことやってるっていうのはこれを聴いてもらえれば分かると思うし、その曲たちを今だから全部ちゃんと肯定できるっていうことをすごく感じたんですよね。新曲から始まって新曲で終わるっていう流れからも、その間にある曲は筋が通って聴こえない?っていうふうに今は言えるし。」
──実際に、作品の中でいろいろなことをやってきたNICOですけど、“心のもっと奥底の扉を開放する感じ”っていう、曲を通して伝えんとしていることとか、根本は…
古村「変わってないです、はい(笑)。」
光村「そうだね。その表現の仕方が変わっただけだし、共有の仕方が変わってるだけで。一方的に球を投げつけるだけじゃなくて、そのボールをみんなで、お客さんと一緒になって転がすみたいな。そういう変化は、ベスト盤の中から感じてもらえるんじゃないかな。それと同時に、今回スタジオセッションをやってみて、昔の曲は全然曲が悪かったわけじゃないんだなって感じられたのは本当良かった。」
対馬「うん。曲は生きてるんだな、っていうか。全然昔から言ってること変わんねーよ、っていうことに気付けてるか気付けてないかっていう違いは大きいよなっていうのが、今回こういう試みをやってみて感じたな。で、そうすると、“俺、もっと良くなるぜ!”ってこの曲たちが言い出すような感覚にもなって、それがすごく自分をワクワクさせるし。」
──新しい扉を開けたというか、新たなところへ向かおうしている感じは、新曲2曲で挟まれている曲順にも表れてると思います。「ローハイド」の歌詞じゃないですけど、このスピード感で駆け抜けてやるぜ、みたいな今の意志も。
対馬「そうです! その意識のもとで、今回の新曲作りもそうだし、武道館に向けてもそうだし、その先も、さらにその先へも、っていう。そういう姿勢で動いてるんです。」
光村「それでいて、とにかく自分の背中も押してくれるような曲が書きたかったんで。これからの始まりを、今の自分たちがやれる最高のやり方で、最高だと思ってる新しいやり方で表現するっていうのが、今回の新曲が生まれたそもそもの背景でしたね。俺たちにとってのリベンジになる武道館へ向かってっていう気持ちになると自然に曲が書きたくなってきたし、この「ローハイド」の、原点にしてすでに頂点みたいなすごい勢いがまず鳴らせないとその先の曲も出せないよなって。それぐらい、大事なターニングポイントになってる曲ですね。」
坂倉「本当そうだね。新曲を作ってた中で良い曲は他にもいっぱいあったんですけど、この曲は本当に今の自分たちの宣言になってたんですよね。だから、この1曲があれば十分だったというか、“今、言いたいのはこれです”っていう。」
光村「うん、そう。とは言いながら、最後に「パンドーラ」が入っちゃったんですけど(笑)。」
古村「予定外だった、それは(笑)。」
──新境地を拓いたというか、まさに“パンドーラの箱”を開けたような感覚?(笑)
光村「(笑)。今回の新曲は、今、このタイミングでしか作らない曲じゃないかと思います。特に「ローハイド」はサビにくると、今までの歴史が、ね…。走馬灯のように蘇ってきて、演奏してて、なんかいろいろ込み上げてくるというか。」
──あっ、ヤバい! 武道館、もしかしたら、目のあたりから込み上げてあふれてくるものがあるかも…
光村「ヤバいな(笑)。「ローハイド」だけで新曲はいいんじゃないかっていう提案をみんなにした時に、俺はこの1曲だけで武道館は感動できる、と。そういう曲だと思ってるからベストは1曲で良いと思ってたところから、さらに「パンドーラ」っていう新しいものも生まれて。だから、武道館はお客さんの反応よりも、自分内反応っていうか(笑)。自分内化学反応がなんか起こるかもしれないなと、そういう状態に持っていきたいなっていう気持ちではいますけどね。」
取材:道明利友
記事提供元:
記事リンクURL ⇒
※この記事をHPやブログで紹介する場合、このURLを設置してください。
NICO Touches the Walls 新着ニュース・インタビュー
新着ニュース
-
 新生HOT DOG CAT、初の新曲披露公演で、1周年ワンマン公演を発表!!2026-02-12
新生HOT DOG CAT、初の新曲披露公演で、1周年ワンマン公演を発表!!2026-02-12 -
 2月19日(木)19時『いじくりROCKS!』#72 ゲストには3月に幕張メッセでのワンマ...2026-02-12
2月19日(木)19時『いじくりROCKS!』#72 ゲストには3月に幕張メッセでのワンマ...2026-02-12 -
 生配信番組『CHAQLA.の部屋』2月16日(月)19時、MAVERICKチャンネルにて放送決...2026-02-10
生配信番組『CHAQLA.の部屋』2月16日(月)19時、MAVERICKチャンネルにて放送決...2026-02-10 -
 陰陽座 ライヴアルバム『吟澪灑舞』ジャケット写真公開!2026-02-06
陰陽座 ライヴアルバム『吟澪灑舞』ジャケット写真公開!2026-02-06 -
 当日の料金は“無料”。LAY ABOUT WORLD、12ヶ月連続ワンマン公演がスタート!!!2026-02-06
当日の料金は“無料”。LAY ABOUT WORLD、12ヶ月連続ワンマン公演がスタート!!!2026-02-06 -
 Blu-ray「HEKIRU SHIINA 30th ANNIVERSARY LIVE 〜HARMONY STAR〜」2月14日(土)...2026-02-04
Blu-ray「HEKIRU SHIINA 30th ANNIVERSARY LIVE 〜HARMONY STAR〜」2月14日(土)...2026-02-04 -
 CHAQLA.「CHAQLA.ONEMAN TOUR チャネリング」 ツアーファイナル 渋谷WWW X公演...2026-02-03
CHAQLA.「CHAQLA.ONEMAN TOUR チャネリング」 ツアーファイナル 渋谷WWW X公演...2026-02-03 -
 vistlip、通算9枚目となるニューアルバム「DAWN」、4月1日に発売決定。2026-02-02
vistlip、通算9枚目となるニューアルバム「DAWN」、4月1日に発売決定。2026-02-02 -
 MUCCのヴォーカル・逹瑯が、待望のニューシングル『checkmate』リリース決定、新...2026-02-02
MUCCのヴォーカル・逹瑯が、待望のニューシングル『checkmate』リリース決定、新...2026-02-02 -
 L’Arc-en-Ciel、SUMMER SONIC 2026 ヘッドライナー出演決定2026-02-02
L’Arc-en-Ciel、SUMMER SONIC 2026 ヘッドライナー出演決定2026-02-02 -
 SAY-LA、3月31日にシングル『半透明スワロフスキー』を発売2026-01-30
SAY-LA、3月31日にシングル『半透明スワロフスキー』を発売2026-01-30 -
 湊人(ミスイ)×Ruiza(Ruiza BAND/Ruiza solo works/D) ミニ対談が到着!!2026-01-30
湊人(ミスイ)×Ruiza(Ruiza BAND/Ruiza solo works/D) ミニ対談が到着!!2026-01-30 -
 「産休制度」のあるVenus Parfaitへ、独身の仲谷明香(元AKB483期生)が加入!!!!!2026-01-29
「産休制度」のあるVenus Parfaitへ、独身の仲谷明香(元AKB483期生)が加入!!!!!2026-01-29 -
 the god and death stars、新体制によるニューアルバムリリース&ワンマンライブ...2026-01-26
the god and death stars、新体制によるニューアルバムリリース&ワンマンライブ...2026-01-26 -
 上月せれな、元日に行った4時間近くに及ぶワンマン公演で全51曲を熱唱!!2026-01-26
上月せれな、元日に行った4時間近くに及ぶワンマン公演で全51曲を熱唱!!2026-01-26 -
 昨年、関西万博や海外で行われた4つのJAPAN FESTIVALのステージに立った中島晴香...2026-01-26
昨年、関西万博や海外で行われた4つのJAPAN FESTIVALのステージに立った中島晴香...2026-01-26 -
 唯(umbrella)、ソロミニアルバム『独楽』リリース&先行試聴イベント開催決定!2026-01-25
唯(umbrella)、ソロミニアルバム『独楽』リリース&先行試聴イベント開催決定!2026-01-25 -
 ピンクの衣装も超かわいい夢乃みゆ(antares)の生誕祭を開催。彼女たち、この界隈...2026-01-23
ピンクの衣装も超かわいい夢乃みゆ(antares)の生誕祭を開催。彼女たち、この界隈...2026-01-23
アーティスト・楽曲・50音検索
人気歌詞ランキング
新着コメント
TUBE / 『あー夏休み』
владимир воронин семья
シェリル・ノーム starring May'n / 『ダイアモンド クレバス/射手座☆午後九時 Don't be late』
Взглянем на XCARDS — сервис, о
котором сейчас говорят.
Совсем недавно наткнулся о цифровой сервис
XCARDS, он дает возможность
создавать онлайн дебетовые карты
чтобы контролировать расходы.
Особенности, на которые я обратил внимание:
Создание карты занимает очень короткое время.
Сервис позволяет выпустить множество
карт для разных целей.
Поддержка работает в любое время суток включая персонального менеджера.
Доступно управление без задержек —
лимиты, уведомления, отчёты, статистика.
На что стоит обратить внимание:
Локация компании: европейская юрисдикция — перед использованием стоит уточнить,
что сервис можно использовать без нарушений.
Комиссии: в некоторых случаях встречаются оплаты за операции, поэтому советую просмотреть договор.
Реальные кейсы: по отзывам поддержка работает быстро.
Защита данных: все операции подтверждаются уведомлениями, но всегда
лучше не хранить большие суммы на карте.
Общее впечатление:
Судя по функционалу, XCARDS может стать
удобным инструментом в сфере финансов.
Платформа сочетает скорость, удобство и гибкость.
Как вы думаете?
Пробовали ли подобные сервисы?
Напишите в комментариях Виртуальные карты для бизнеса
シェリル・ノーム starring May'n / 『ダイアモンド クレバス/射手座☆午後九時 Don't be late』
Что такое XCARDS — сервис, о котором сейчас говорят.
Буквально на днях заметил о интересный бренд XCARDS, он помогает создавать онлайн карты чтобы управлять бюджетами.
Ключевые преимущества:
Выпуск занимает всего считанные минуты.
Платформа даёт возможность оформить множество карт для разных целей.
Есть поддержка в любое время суток включая персонального менеджера.
Есть контроль без задержек — транзакции, уведомления, аналитика — всё под рукой.
Возможные нюансы:
Регистрация: европейская юрисдикция — желательно убедиться, что
сервис можно использовать без
нарушений.
Финансовые условия: возможно,
есть скрытые комиссии, поэтому лучше внимательно прочитать договор.
Отзывы пользователей: по отзывам поддержка работает быстро.
Надёжность системы: внедрены базовые меры безопасности, но всё равно советую не хранить большие суммы
на карте.
Вывод:
В целом платформа кажется
отличным помощником для маркетологов.
Платформа сочетает скорость, удобство
и гибкость.
Как вы думаете?
Пользовались ли вы XCARDS?
Поделитесь опытом — будет интересно сравнить.
Виртуальные карты для бизнеса
シェリル・ノーム starring May'n / 『ダイアモンド クレバス/射手座☆午後九時 Don't be late』
Взглянем на XCARDS — платформу, которая меня заинтересовала.
Буквально на днях услышал на новый проект XCARDS, он помогает создавать цифровые банковские карты для онлайн-платежей.
Основные фишки:
Карту можно выпустить за ~5 минут.
Платформа даёт возможность создать
любое число карт — без ограничений.
Поддержка работает круглосуточно включая живое
общение с оператором.
Доступно управление в реальном времени — лимиты, уведомления, отчёты, статистика.
Возможные нюансы:
Локация компании: европейская юрисдикция
— желательно убедиться, что это соответствует местным требованиям.
Стоимость: карты заявлены как “бесплатные”, но дополнительные сборы, поэтому рекомендую внимательно прочитать договор.
Реальные кейсы: по публикациям на форумах поддержка работает
быстро.
Надёжность системы: сайт использует шифрование, но всё
равно советую не хранить большие суммы
на карте.
Общее впечатление:
В целом платформа кажется
удобным инструментом в онлайн-операций.
Он объединяет удобный интерфейс,
разнообразие BIN-ов и простое управление.
Как вы думаете?
Пробовали ли подобные сервисы?
Расскажите, как у вас работает Виртуальные карты для онлайн-платежей
シェリル・ノーム starring May'n / 『ダイアモンド クレバス/射手座☆午後九時 Don't be late』
Вау, прекрасно веб-сайт. Спасибо...
Посетите также мою страничку
Квартиры на сутки