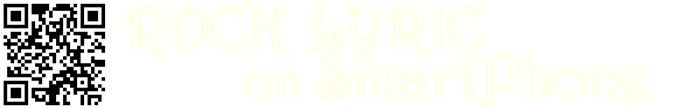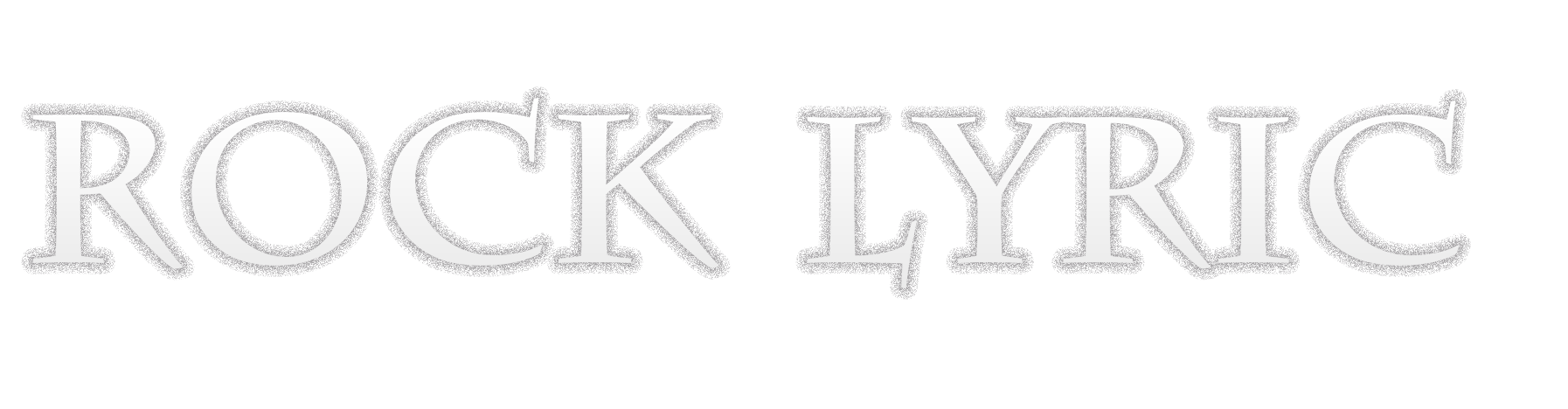2014-01-20
【Dragon Ash】3年振りとなる剥き出しのニューアルバム!

Dragon Ashが10thオリジナルフルアルバム『THE FACES』を完成させた。さまざまな出来事を乗り越えて6人のメンバーから届けられた今作は、音楽的なテーマより何より、彼らの意思が聴こえてくる。まるで子供のように自然に産み落とされたような表情のある14曲。感動的な傑作だ。
【血と骨と肉だけで全曲を作る感覚 6人にとっては処女作だからね】
──まず、『THE FACES』を作り終えた直後の率直な感想は?
桜井「えーっとね、すごくそれ訊かれるんだけど、“あぁぁぁぁ…”(仰け反る)っていう(笑)。」
──言葉じゃないんですね(笑)。
桜井「マスタリングが終わっても、“できたぁ…”みたいな感じでしたね。“やったー!”っていう感じじゃなく。」
──でも、それって達成感があったからですよね。
桜井「うん、それだけエネルギーは入ってるはずですね。」
──その消耗した感じって、今までの作品と比べても大きかったですか?
桜井「そうかもね。みんなで一斉に“疲れた”って言ったことは、そんなになかったかも。」
──その心境は、Kjさんも一緒?
Kj「(頷く)。」
桜井「人一倍ですよ。」
Kj「でも間違いなく、過去最高の達成感のほうが大きいですけど。ただ、完成した12時間後に、俺、石巻でライヴやってましたからね(笑)。サク(桜井)は終わった瞬間にセットリストを考えてましたから。カオスだね。」
桜井「まぁ、逆に言うと、それくらいギリギリまで引っ張ったっていうか。」
──詰めて詰めて作りたかったのですか?
桜井「そうですね。12曲が完成して、“別にこれでも出せるよね”っていう状況ではあったんですけど、でもあと2日間レコーディングの日程があって、“やっぱこれ入れたいよね”っていう時に、「The Live feat.KenKen」と「Curtain Call」を録ったんです。」
──なるほど。では、制作に入る前に、次はこんなアルバムにしたいというビジョンはあったのですか?
Kj「どうせやるなら、過去の全ての作品を超越できるアルバムを作りたいから。アルバムを作るなら覚悟してやりたいっていう話はしたような気がします。スパイスだったり、実験的要素とかではなく、血と骨と肉だけで全曲を作る感覚。」
──ジャンルやテーマに縛られることなく、自然と自分たちから生まれてくるものを大切にしたというか。
Kj「そうだね。「Introduction」「The Show Must Go On」の次の2曲目だから、こう思っているって歌ってから(アルバムに)入っていくっていう、細々したテーマはあったけど。」
──前作から時間が空いているし、いろんなことがあったし、それが今作への思いを引き寄せたところはありますか?
Kj「うん。…でも、意外と早産な曲が多かったかな。今までよりも早かったくらいじゃないかな。 」
──曲を産み落としていきたいっていう、テンションが高い状態だったのですか?
Kj「そうだね。すっげぇ切迫感がある生活をしていたね。産まなきゃ、産まなきゃ、みたいになって、研ぎ澄まされていたような気がする。肉体が疲労を感じる前に、もっと遠くへいっている、みたいな感じだった。」
──それは、しんどくても分からないような感じですか?
Kj「うん。レコーディング自体は俺たち、大好きだから。楽しいしかないからさ。すげぇ話し合うタイプのグループだけど。音楽的にはすごく緻密なことをやっていても、そう聴こえないようにするっていうか。緻密さが板に付きすぎて自然に見える、みたいな感覚だよね、俺らにとっては。」
──その“産まなきゃ”っていう思いは“The Show Must Go On”っていう言葉に背中を押されたところもあるのですか?
Kj「うん。誰よりも音楽が好きでさ、結束の高いバンドがさ、やりたくてもやれない時期が長くあるってさ、かなり辛いことだから。いざやれるってなったら、すごかったんじゃない? みんなの、やりたがり2000な感じが(笑)。」
桜井「(笑)。」
Kj「常に何本も飲んだような状態で生活してるっていう(笑)。まぁ、単純にリハスタで揃うだけで、喜びを抱けるわけだからさ。こういうことが起こんなければ、それに気付けないっていう未熟さも痛感したけど、それはみんなも思っていると思う。単純に楽器を弾くだけで、こんなに幸福なことはないとか、“もっと、ここはこうしようよ”って話せる相手がいることの幸せとか、俺らはめっちゃ分かってるから。」
──桜井さんも同感ですか?
桜井「もちろん。やっぱり生きていく上で、これほど刺激があって、楽しくて、やり甲斐があって、っていう職業は他にないと思うんですよね。だから、単純にそれを続けられるっていうことが一番幸福ですよね。長くやってると、そういう小さなことを忘れちゃうこともあるのかもしれないし、よりそこが強固なものになったというか。」
──制作では、やりたくてもやれない時期に溜め込んでいた思いやアイデアをぶつけた感じですか?
桜井「うーん、溜め込んでいたというよりかは、よりチャレンジ精神があったかな。“ここでこれをやんなくてもいいや”とか、そういうのも取りあえずやってみるっていう。だから、建志(kj)が持ってきたものに対して、100点を採るんであれば、そのままやればいい話だけど、“こうじゃない”って言われるかもしれないけど…ドラマーにしか分からない熱さもあるじゃないですか、そういうものも当て込んでいったりとか。それで、どうしてもここだけはこうしてくれとか、ここは歌と絡みがあるからこうしてるんだって言われれば、その通りに直したりとか。そういうのがより多かったかな。」
──今までのほうが、Kjさんの曲に忠実にやっていた?
桜井「んー、もちろん自分のやり方も入れてはいたけど、今回はサウンド面とかもこだわったかな。」
──そうやって、ひとりひとりが自分の色を濃くしているからかもしれないですけど、今作のトーンは全体的にエモーショナルですよね。とても人間臭いというか。
Kj「うーん…まぁ、6人にとっては処女作だからね。その気合い入りっぷりったら相当だった。歯抜けの状態で、今までの自分たちを超越しようとしているわけだからさ。そりゃあもう、みんなが無理して、補い合って、グルーブを作ってくっていうことでしかないからさ。」
──全員が少しずつ背伸びをした、というか。
Kj「そういうこと、そういうこと。歯が抜けてても、今までよりカッコ良く見せるわけだからね(笑)。そりゃあ、他が凄まじくカッコ良くないといけないよね。」
【それが伝染していって 俺たちの現在のテーマに昇格した】
──Kjさんがベースを弾いているところも、そういうところとつながってくるのですか?
Kj「いや、それはミーティングでそうなった。俺が決めたわけじゃないけど、“建志が弾くのが必然なんじゃない?”って。このアルバムが作れる確信があるからそうなったわけじゃなくて、一回、一番分かりやすいかたちから始めてみようっていう。」
──今までになかったチャレンジではありますよね?
Kj「ドラゴンで弾いてないだけだけどね。でも、だいぶ練習はしたよ、引かれるくらい(笑)。」
桜井「地味な降谷建志ね(笑)。」
──何だか、これだけキャリアがあるアーティストから練習っていう言葉を聞くと、微笑ましいです(笑)。
Kj「でも、俺、前から練習の鬼だからね。人の倍じゃきかないくらい練習してるからね。そこは、あまり苦になるタイプじゃないから。ただ、要はそれがカッコ良いかどうかじゃん。6人でやるのがカッコ良いんじゃなくて、できた音がカッコ良いかどうかだから、問題はそこだよね。」
──じゃあ、カッコ良いものができて、いちベーシストとしてもひと安心しているんじゃないですか?
Kj「そうだね(笑)。」
桜井「いちベーシストとして評価されたいですよね(笑)。」
Kj「弾きたいわ~、Charaさんの隣とかで。」
──それはKenKenさんです(笑)。その全ては“The Show Must Go On”っていう言葉につながってくる気がするのですが、この言葉を思い付いたのはいつ頃なのですか?
Kj「だいぶ前からじゃないかな。ことわざ的には“やり遂げよう”っていう意味だからね。今回で言えば、アルバムを作ろうっていうことだよね。でも、最初は思い付きで言ったんだけどね。来年の抱負は?みたいにフリップで書く軽いタッチの時に“The Show Must Go On”って出てきて、それが伝染していって、俺たちの現在のテーマに昇格したっていう感じですね。」
桜井「いつの間にか共有言語になった。」
Kj「そうそうそう。分かりやすいシンボルで良かったと思うけど。アルバムの説得力も増したし、そっから見えたものは確かにあるよね。」
──あと、最新シングル「Lily」を聴いていても思ったのですが、Dragon Ashは自分たちだけではなく、ファンも含めたみんなで作っている感覚ってあるのでは?
Kj「そうだね。人一倍ファンに支えられているバンドっていうことは、ほんっとに昔から俺たちは自覚してるからね。」
桜井「それがより如実になった感じがしますよね。12月4日に「Lily」をリリースしてライヴをやったんですけど、そこでもすごく実感しました。アルバムの制作が終わってすぐで大変な時期だったけど、やって良かったですね。フェスとかは出ていたけど、自分らを観たいと思って来てくれたお客さんしかいない場所でライヴをやることは大事だと思いました。それが長らくできていなかったから。だから、この『THE FACES』のツアーは、よりいいものにしたいと思っています。俺たちにとっても、お客さんにとっても。」
──ライヴの絵が浮かぶっていうところでは、ラストを温かく締め括る「Curtain Call」が顕著ですね。
Kj「うん。「Curtain Call」は急遽歌入りの曲になって。ライヴの最後にいつもやれる曲になりそうだなって。」
──この曲もそうだし、どの曲も温かい表情をしていますよね。もちろん、いろんな感情が詰まっているのでしょうけど。
桜井「エモーショナルっていうところに通じるかもしれないですね。怒ってても、悲しんでても、ちゃんと理由がある。だから、結局温かく見えるっていう。」
──確かに。アルバムとしてまとめた時に、こんな顔になるんだ!っていうのは、発見だったのでは?
桜井「うん。曲順を決めるのがほんとに大変だったくらい、一曲一曲が持つ力が強いんですよね。所謂アルバムを作る時って、だいたいこの辺にアルバム用な曲があるよねとか、そういう流れってあるじゃないですか。でも今回、全曲シングルカットできるくらいのパワーがある曲たちを14曲並べて…まぁ、頭とケツは決まっていましたけど、それ以外の並びは、みんな持っているイメージがバラバラでしたね。それくらい、いかようにもなるアルバムだった。」
──本当に“THE FACE”というタイトルがピッタリですけど、いつくらいにこのタイトルは決まったのですか?
Kj「「The Show Must Go On」と一緒に「Introduction」も持っていったんで、制作時期の中盤には付いていましたね。自分たちの顔となる作品を作ろう、ギミックとかお化粧なしに。そういうアルバムに向かってるなって思っていたから。」
──ギミックやお化粧も嫌いじゃない。でも、今はすっぴんなアルバムを作りたかったんですね。
桜井「そのモードになったんですよね。」
取材:高橋美穂
記事提供元:
記事リンクURL ⇒
※この記事をHPやブログで紹介する場合、このURLを設置してください。
Dragon Ash 新着ニュース・インタビュー
新着ニュース
-
 新生HOT DOG CAT、初の新曲披露公演で、1周年ワンマン公演を発表!!2026-02-12
新生HOT DOG CAT、初の新曲披露公演で、1周年ワンマン公演を発表!!2026-02-12 -
 2月19日(木)19時『いじくりROCKS!』#72 ゲストには3月に幕張メッセでのワンマ...2026-02-12
2月19日(木)19時『いじくりROCKS!』#72 ゲストには3月に幕張メッセでのワンマ...2026-02-12 -
 生配信番組『CHAQLA.の部屋』2月16日(月)19時、MAVERICKチャンネルにて放送決...2026-02-10
生配信番組『CHAQLA.の部屋』2月16日(月)19時、MAVERICKチャンネルにて放送決...2026-02-10 -
 陰陽座 ライヴアルバム『吟澪灑舞』ジャケット写真公開!2026-02-06
陰陽座 ライヴアルバム『吟澪灑舞』ジャケット写真公開!2026-02-06 -
 当日の料金は“無料”。LAY ABOUT WORLD、12ヶ月連続ワンマン公演がスタート!!!2026-02-06
当日の料金は“無料”。LAY ABOUT WORLD、12ヶ月連続ワンマン公演がスタート!!!2026-02-06 -
 Blu-ray「HEKIRU SHIINA 30th ANNIVERSARY LIVE 〜HARMONY STAR〜」2月14日(土)...2026-02-04
Blu-ray「HEKIRU SHIINA 30th ANNIVERSARY LIVE 〜HARMONY STAR〜」2月14日(土)...2026-02-04 -
 CHAQLA.「CHAQLA.ONEMAN TOUR チャネリング」 ツアーファイナル 渋谷WWW X公演...2026-02-03
CHAQLA.「CHAQLA.ONEMAN TOUR チャネリング」 ツアーファイナル 渋谷WWW X公演...2026-02-03 -
 vistlip、通算9枚目となるニューアルバム「DAWN」、4月1日に発売決定。2026-02-02
vistlip、通算9枚目となるニューアルバム「DAWN」、4月1日に発売決定。2026-02-02 -
 MUCCのヴォーカル・逹瑯が、待望のニューシングル『checkmate』リリース決定、新...2026-02-02
MUCCのヴォーカル・逹瑯が、待望のニューシングル『checkmate』リリース決定、新...2026-02-02 -
 L’Arc-en-Ciel、SUMMER SONIC 2026 ヘッドライナー出演決定2026-02-02
L’Arc-en-Ciel、SUMMER SONIC 2026 ヘッドライナー出演決定2026-02-02 -
 SAY-LA、3月31日にシングル『半透明スワロフスキー』を発売2026-01-30
SAY-LA、3月31日にシングル『半透明スワロフスキー』を発売2026-01-30 -
 湊人(ミスイ)×Ruiza(Ruiza BAND/Ruiza solo works/D) ミニ対談が到着!!2026-01-30
湊人(ミスイ)×Ruiza(Ruiza BAND/Ruiza solo works/D) ミニ対談が到着!!2026-01-30 -
 「産休制度」のあるVenus Parfaitへ、独身の仲谷明香(元AKB483期生)が加入!!!!!2026-01-29
「産休制度」のあるVenus Parfaitへ、独身の仲谷明香(元AKB483期生)が加入!!!!!2026-01-29 -
 the god and death stars、新体制によるニューアルバムリリース&ワンマンライブ...2026-01-26
the god and death stars、新体制によるニューアルバムリリース&ワンマンライブ...2026-01-26 -
 上月せれな、元日に行った4時間近くに及ぶワンマン公演で全51曲を熱唱!!2026-01-26
上月せれな、元日に行った4時間近くに及ぶワンマン公演で全51曲を熱唱!!2026-01-26 -
 昨年、関西万博や海外で行われた4つのJAPAN FESTIVALのステージに立った中島晴香...2026-01-26
昨年、関西万博や海外で行われた4つのJAPAN FESTIVALのステージに立った中島晴香...2026-01-26 -
 唯(umbrella)、ソロミニアルバム『独楽』リリース&先行試聴イベント開催決定!2026-01-25
唯(umbrella)、ソロミニアルバム『独楽』リリース&先行試聴イベント開催決定!2026-01-25 -
 ピンクの衣装も超かわいい夢乃みゆ(antares)の生誕祭を開催。彼女たち、この界隈...2026-01-23
ピンクの衣装も超かわいい夢乃みゆ(antares)の生誕祭を開催。彼女たち、この界隈...2026-01-23
アーティスト・楽曲・50音検索
人気歌詞ランキング
新着コメント
TUBE / 『あー夏休み』
владимир воронин семья
シェリル・ノーム starring May'n / 『ダイアモンド クレバス/射手座☆午後九時 Don't be late』
Взглянем на XCARDS — сервис, о
котором сейчас говорят.
Совсем недавно наткнулся о цифровой сервис
XCARDS, он дает возможность
создавать онлайн дебетовые карты
чтобы контролировать расходы.
Особенности, на которые я обратил внимание:
Создание карты занимает очень короткое время.
Сервис позволяет выпустить множество
карт для разных целей.
Поддержка работает в любое время суток включая персонального менеджера.
Доступно управление без задержек —
лимиты, уведомления, отчёты, статистика.
На что стоит обратить внимание:
Локация компании: европейская юрисдикция — перед использованием стоит уточнить,
что сервис можно использовать без нарушений.
Комиссии: в некоторых случаях встречаются оплаты за операции, поэтому советую просмотреть договор.
Реальные кейсы: по отзывам поддержка работает быстро.
Защита данных: все операции подтверждаются уведомлениями, но всегда
лучше не хранить большие суммы на карте.
Общее впечатление:
Судя по функционалу, XCARDS может стать
удобным инструментом в сфере финансов.
Платформа сочетает скорость, удобство и гибкость.
Как вы думаете?
Пробовали ли подобные сервисы?
Напишите в комментариях Виртуальные карты для бизнеса
シェリル・ノーム starring May'n / 『ダイアモンド クレバス/射手座☆午後九時 Don't be late』
Что такое XCARDS — сервис, о котором сейчас говорят.
Буквально на днях заметил о интересный бренд XCARDS, он помогает создавать онлайн карты чтобы управлять бюджетами.
Ключевые преимущества:
Выпуск занимает всего считанные минуты.
Платформа даёт возможность оформить множество карт для разных целей.
Есть поддержка в любое время суток включая персонального менеджера.
Есть контроль без задержек — транзакции, уведомления, аналитика — всё под рукой.
Возможные нюансы:
Регистрация: европейская юрисдикция — желательно убедиться, что
сервис можно использовать без
нарушений.
Финансовые условия: возможно,
есть скрытые комиссии, поэтому лучше внимательно прочитать договор.
Отзывы пользователей: по отзывам поддержка работает быстро.
Надёжность системы: внедрены базовые меры безопасности, но всё равно советую не хранить большие суммы
на карте.
Вывод:
В целом платформа кажется
отличным помощником для маркетологов.
Платформа сочетает скорость, удобство
и гибкость.
Как вы думаете?
Пользовались ли вы XCARDS?
Поделитесь опытом — будет интересно сравнить.
Виртуальные карты для бизнеса
シェリル・ノーム starring May'n / 『ダイアモンド クレバス/射手座☆午後九時 Don't be late』
Взглянем на XCARDS — платформу, которая меня заинтересовала.
Буквально на днях услышал на новый проект XCARDS, он помогает создавать цифровые банковские карты для онлайн-платежей.
Основные фишки:
Карту можно выпустить за ~5 минут.
Платформа даёт возможность создать
любое число карт — без ограничений.
Поддержка работает круглосуточно включая живое
общение с оператором.
Доступно управление в реальном времени — лимиты, уведомления, отчёты, статистика.
Возможные нюансы:
Локация компании: европейская юрисдикция
— желательно убедиться, что это соответствует местным требованиям.
Стоимость: карты заявлены как “бесплатные”, но дополнительные сборы, поэтому рекомендую внимательно прочитать договор.
Реальные кейсы: по публикациям на форумах поддержка работает
быстро.
Надёжность системы: сайт использует шифрование, но всё
равно советую не хранить большие суммы
на карте.
Общее впечатление:
В целом платформа кажется
удобным инструментом в онлайн-операций.
Он объединяет удобный интерфейс,
разнообразие BIN-ов и простое управление.
Как вы думаете?
Пробовали ли подобные сервисы?
Расскажите, как у вас работает Виртуальные карты для онлайн-платежей
シェリル・ノーム starring May'n / 『ダイアモンド クレバス/射手座☆午後九時 Don't be late』
Вау, прекрасно веб-сайт. Спасибо...
Посетите также мою страничку
Квартиры на сутки